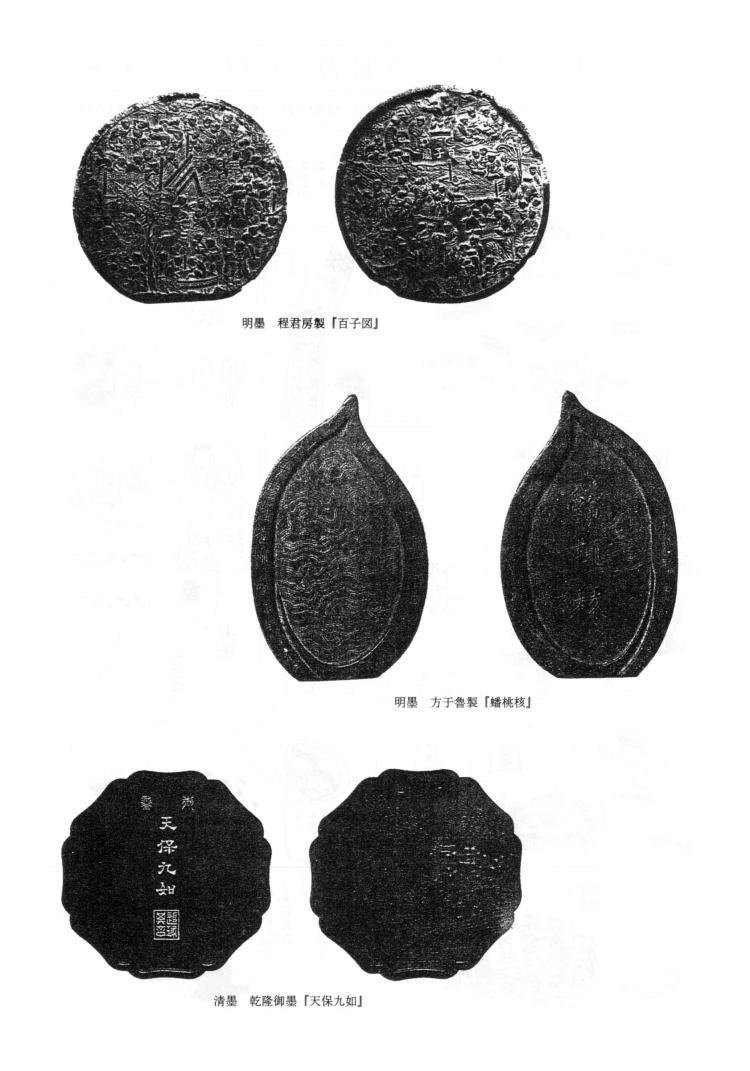文房四宝6 ◆◇◆HOMEにもどる
墨(3)
*************************************************************************************
墨は、煤(すす)と膠(にかわ)を練り合わせて、香料を加えて固めたものです。
煤は、身近な存在としてはローソクの炎の先から出る黒い煙や石油ストーブの消化の時にゆらゆらと立ちのぼる黒い煙に含まれるものです。墨に使われる煤は松脂(まつやに)や菜種油(なたねあぶら)などを燃やして得られたものです。松脂を燃やして得た煤を原料とする墨は松煙墨(しょうえんぼく)と呼ばれ、莱種油などの植物油を燃やして得た煤を原料をする墨は油煙墨(ゆえんぼく)と呼ばれます。また近年では鉱物油を燃やして得た煤を原料とする墨は、洋煙墨(ようえんぼく)という言葉で呼ばれます。現在の墨の原料としては80パーセントが鉱物油によるものです。
膠は、普通にはゼラチンと呼ばれるもので、動物の皮や軟骨などに含まれる蛋白質(たんぱくしつ)です。膠の特性としては、温水に解けやすく、接着力もあり、冷やすとゼリー状に固まります。「煮こごり」といって、冷蔵庫にいれた煮魚の汁が固まるのも冷やすとゼリー状に固まりやすい膠によるものです。墨に使われる膠は、牛などの骨や皮を長時間煮ることによって得られたものです。墨に使う香料は、楠(くすのき)からとった樟脳(しょうのう)を精製したものを使います。樟脳は、家庭ではタンスなどに入れる防虫剤として使われています。和墨(わぼく・我が国でつくられた墨)は良い香りがします、書道教室などで墨を使うと独特の香りが部屋に満ちあふれるのは、墨に加えられた香料が磨墨(まぼく・墨をすること)により一層匂いたつためです。また、香料には入間の精神を安定させる鎮静作用があるため、心のおちつきを自然に得られるよう絶妙な効果があります。おもしろいことに本家ほんもとである唐墨(とうぼく・中国製のもの)はあの独特の香りがしません。これは香料が加えられていないことによるものです。どうやら香料を加えたのは日本のオリジナルのようです。
磨墨は、墨色を決める重要なポイントです。どんなに良い墨を高価な値段で求めても磨墨の方法を知らないでは、決してその墨本来の墨色を得ることはできません。名人の筆跡というものを実際に鑑賞しますと、その字姿の美しさ素晴らしさに心洗われますとともに墨色のかがやきに驚かされます。それが昨日今日の筆跡ならともかくも二百年、四百年と歳月を経たものが、まるで昨日書かれたように墨色が衰えていないことに尊ささえ感じるものです。この墨色を出すための工夫が磨墨のポイントです。『考槃餘事(こうはんよじ)』という本は、文人が使う文房具について書いたものです。そこでは墨の取り扱いについて次ぎのように書かれています。少しながいですが大意を引用します。
……墨の上手な取り扱いかたは、重さは軽いもの をえらび、煤はきめの細かいものをえらび、 匂いはないものがよく、磨っても音のしないものをえらぶ。硯に新しい水をそそぎ、力を入れないようにして磨る。いそいで磨ると熱くなり、熱くなると沫(あわ)ができるのを嫌う。磨ったものはすぐに使い、磨ったものをながくそのままにしておいてはいけない。埃(ほこり)で墨がよごれ、膠でどろどろになってしまう。使い終わったら硯を洗っておくように心がけ、墨のかすを一ぱいつけておいてはいけない。ながく保存しておいた墨は膠が枯れて、使いやすくなるものである。……『考槃餘事』(屠隆・とりゅう)墨箋(ぼくせん)より
磨墨のポイントはただ一つですね、力を入れないようにして磨ることです。そして磨りあがった墨はすぐに使うこと。このことを是非試してみて下さい。
磨墨後は、墨のすり口の水分を紙などで拭き取っておくようにします、これをしないと墨のひび割れの原因になります。湿度には特に敏感ですので注意を要します。直射日光があたるところ、ストーブのちかく、クーラーなどの風が直接あたり急激に乾燥するところは好ましくありません。乾燥が高いところは墨に割れが生じやすく、パチパチと音がする時は箱に収めるなどして外気を避けるようにすると良いでしょう、また湿度の高いところはかびが生じやすいので、ぬれた筆と一緒におくのはあまり感心しません。さらに落としたり強くぶつけたりすると割れてしまうことがありますので取り扱いに十分に注意が必要です。
初出/『菅城』588号(平成7年8月)
再出/『拓美』359号(平成7年10月)
Web版/平成18年3月再編・加筆